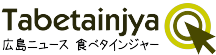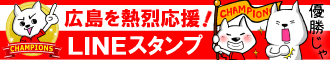公開:2018/06/22 伊藤 みさ │更新:2019/08/14
2日目のカレーもヤバイ?!食中毒に注意したい 6つの予防法
- タイトルとURLをコピー
- 広島ニュース


食中毒を予防するために知っておきたいポイントを6つのシーン別にご紹介します。特に油断しやすい2日目のカレーにはご注意を!
梅雨から夏にかけて多い食中毒。湿度の高い日や気温が高くなってくると、常温保存していたものが傷んでいた…という実感・危機感を感じた方もいらっしゃるかもしれません。

食中毒予防の基本は「手洗いや食品の十分な加熱」ですが、それだけでは不十分。
厚生労働省が推奨する、食品・各家庭で出来る、注意しておきたい6つの「シーン別 食中毒対策法」を以下にご紹介します。
食中毒の症状と予防法
食中毒になると、激しい下痢や腹痛に襲われます。特に、下痢は1日20回を超えることも。これに次いで、発熱や嘔吐など辛い症状が食後1から5時間の間に襲ってきて、
食中毒になってしまうと、とてもつらい。食中毒を避けるために注意すべきポイントを、以下に6つご紹介します。
【食中毒予防ポイント1】お買物時
- 生鮮食品は期限表示を確認し新鮮なものを選ぶ
- 冷蔵・冷凍が必要な食品は買い物の最後に
- 肉・魚はそれぞれ分けて包む
【食中毒予防ポイント2】食品を保存する時
- 冷蔵・冷凍が必要な食品を常温で放置しない
- 冷蔵庫内では肉汁などが他の食品につかないようにする
- 冷蔵庫の詰め過ぎに注意(冷えにくくなるため、7割程度にする)
- 作業前後・肉・魚・卵の扱い後は必ず手洗いをする
- 生肉・生魚を切った包丁・まな板はすぐに熱湯消毒。他の食品はまな板を変える
- カット野菜も流水でよく洗う
- 調理器具・ふきん・タワシなどは定期的に消毒(漂白剤・煮沸・熱湯)
- 冷凍物の解凍は冷蔵庫内又はレンジで
【食中毒予防ポイント4】調理の時
- 調理前は必ず手洗い(手に怪我をしている場合はビニール手袋などを使用)
- 加熱の基本は「中心部の温度が75度で1分間以上」
- 使いかけの材料は室温に放置しない
【食中毒予防ポイント5】食事の時
- 盛り付けは清潔な手・器具・食器で
- 料理を室温に長く放置しない
【食中毒予防ポイント6】食品が残った時
- 残った食品は早く冷えるよう浅い容器に小分けし冷蔵庫へ
- 温めなおす時は「チン」ではなく鍋に入れて十分加熱する
- 時間が経ちすぎたり、少しでも怪しいと思ったら捨てる
via.厚生労働省パンフレット
特に気を付けたい「お弁当」、2日目のカレーもご注意を
一般家庭で口にするもののうち、調理してから食べるまでに時間のかかるお弁当などは、特に注意が必要。
- 肉・魚は小さ目に切って中心部まで十分に加熱する
- おにぎりは素手ではなくラップに包んで握る
- ゴハンやおかずはよく冷ましてから詰める
- おかずの汁気をよく切ってから詰める(水分が多いと細菌が増える可能性)
- 長時間持ち歩く時は保冷バッグ・保冷剤を活用する
- 車の中など、暑くなる場所に放置しない
- 少しでも“変だな” と感じたものは食べない
などを徹底しましょう。

また、夏場に食べたくなるのが、カレー。香辛料が入り加熱時間も長いため「食中毒にはなりにくいイメージ」がありますが、“一番おいしい” と言われる2日目のカレーは、夏場は要注意です。
一般的にカレーの具材として使われる肉・ジャガイモ・人参・玉ねぎなどの根菜類は、土や水中などに広く存在する「ウエルシュ菌」が潜んでいる可能性も。(あたると下痢や吐き気などの食中毒症状が出るという)
作りたてのカレーならほぼ問題ないようですが、ウエルシュ菌は「空気に触れない場所」「45℃以下」で急激に増殖するといわれているため、数日に分けて楽しむカレーなどの料理は要注意です。
カレーを一晩寝かせたい場合は、荒熱がとれたら冷蔵庫・冷凍庫で保存。食べるときは、まんべんなくよく混ぜ、しっかり加熱してから食べましょう(参考 / ウエルシュ菌)。
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- 広島市街地で打上げ花火!空鞘稲生神社の夏越祭2025
- 徳川で「新作かき氷」ひんやり夏メニューが期間限定で登場
- 広島ドッグフェスタ2025 サマーナイト、愛犬と楽しむ夏イベント
- 西園を全面閉鎖、広島市安佐動物公園に野生のクマ出没
- 広島で友好イベント「モントリオールの日」カナダ名物の販売・ジャズコンサートなど入場無料
- ドラゴンクエストコンサート、広響 夏休みスペシャル2025!