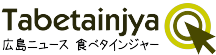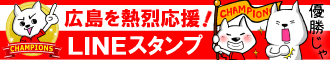公開:2015/09/07 Mika Itoh │更新:2018/07/02
魚に触れて調査船にも乗れる!水産研究所の一般公開で
- タイトルとURLをコピー
- 廿日市市 スポット 観光


年に1度だけ、一般開放している水産研究所。調査船「しらふじ丸」内部も見学することが出来ます。毎年多くの来場者で賑わっているその理由を探りに、訪れてみました!
広島県廿日市市にある、瀬戸内海海区水産研究所が1年に1度の一般公開を2015年9月5日に実施しました。

水産研究所とは主に、海のトラブルである赤潮や有害物質など、漁場環境問題について調査したり、問題解決のための研究等を行っている研究施設。
「研究」と言うと、なんだか難しそうな事をしているイメージですが、一般公開ではどんな事を見たり体験することができるのでしょうか。中を覗きに行ってみました。
水産研究所 一般公開、瀬戸内海の不思議いろいろ
こちらが、瀬戸内海区水産研究所の入口。

水産研究所のゆるキャラ「ふーちゃん(フグと思われる)」がお出迎え。

ちなみに瀬戸内海区水産研究所では、少なくなっている高級魚のトラフグやオコゼなどを育成場で卵から育てて、海へかえすといった事も行っているのだそうです。
会場に入ると、所狭しと海や魚に関する展示やクイズ、体験コーナーなどが用意されています。

「広島湾に住む妖怪」として、私達があまりお目にかかることの無い不思議な形をした生き物を見学することができたり、

小さすぎて目で確認しづらい海の生物などを、顕微鏡で見れたり。

また、船員さんがいろんな場面で使用する様々なロープの結び方も紹介されていて

その中から1種類、実際に結び方を教えてくれるコーナーもあり。
瀬戸内海区水産研究所の屋外で、触れ合いや体験コーナーも
外に出てみると「海藻 押し葉ハガキコーナー」があり、押し花の海藻バージョンを作る体験コーナーがありました。

用意されている色んな種類の海藻から、好みの海藻を選んで

ハガキの裏面に、押し花ならぬ「押し海藻」を好きなように作ると、それを水産研究所の人が預かり乾燥させた後にパウチをして、後日 自宅まで郵送してくれます。しかも無料で。

子供たちが作った作品
また、水産研究所が育てているフグを間近で見ることが出来たり、触れるお魚の体験コーナーがあったりと、

どのコーナーでも水産研究所のスタッフがとても丁寧に説明されていて、それらを子供たちが楽しそうに聞き入っていました。
夏休み期間中の開催なら、いい自由研究の題材になりそうです。
いざ、漁業調査船の中へ!

海岸のほうに歩いていくと、漁業調査船「しらふじ丸」も一般公開されていました。

船に乗り込むと、調査船「しらふじ丸」が航海中にどんな事をするのか?また、船員はどんな風に船で生活しているのか?などを、それぞれの部屋の前で教えて貰えます。

調査船へと踏み込みます!

船員の食事を作る立派なキッチン。ガスは危ないので、すべて電気なのだとか。

しらふじ丸のレーダー。これで島や他の船・筏などとの距離を測ったり、方位を確認することが出来る。ちなみに、電波を使って測っているのだそうですよ。
この他にも、海底までの距離を測る機会や、GPS搭載で航路を決めるカーナビのようなものまで、いろんなものが積まれていました。

しらふじ丸の操縦室。大きな船は見通しが良さそうですが、死角も多いため操縦はレーダーなどが必須なのですね。
無料でふるまい!かき氷サービスも
船を出て水産研究所の建物に向かって歩いて戻ると、

なんと、かき氷の無料サービスまで。

また、受付でもらったパンフレットの袋の中には、お土産のキーホルダーまで入っていました。「押し海藻」のハガキも無料で送ってくれますし、なんて至れり尽くせりのイベントなんでしょうか。無料でここまでやってくれるイベントも、珍しい。
子供だけでなく、大人も含めてかなり来場者が多い事に最初は驚きましたが、それも納得の充実の一般開放でした。
瀬戸内海海区水産研究所 | |
|---|---|
| 住所 | 広島県廿日市市丸石2-17-5 (本所) |
| 問合せ | 0829-55-0666 |
| 備考 | 一般開放は年に1回のみ。(8月下旬または9月初旬頃)/ ホームページ |
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- 星野リゾート【界 宮島】広島初のホテルには石風呂も!場所は宮島口西エリア
- 氷ピクミンが出現!宮島SA「ピクミンテラス」フォトスポットが追加されたよ
- 何これ可愛すぎ…!イルカが宮島沖・大野瀬戸で船に寄り添い泳ぐ風景
- 宮島花火、復活!新たな形「厳島水中花火大会」へ、村上信五がアンバサダー
- 宮島フェリーの松大汽船、クレカの「タッチ決済」を導入開始
- カープ大野寮 若鯉展、宮島口で「出世部屋」を再現・2025年は佐々木選手!