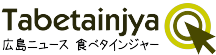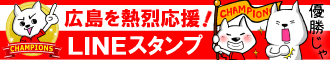公開:2015/08/15 Mika Itoh │更新:2020/08/12
盆灯籠の代わりに塔婆(木札)も、広島のお盆の風景
- タイトルとURLをコピー
- 広島コネタ


広島のお盆も、盆灯籠の代わりに「南無阿弥陀仏」や「倶会一処」と書かれた木札がお墓に供えられた風景が増えてきました。広島県(主に県西部)の風物詩だった盆灯籠が少しずつ減っているようです。
広島県西部では、お盆になるとお墓の周りに盆灯籠を立てる習慣があり、カラフルな灯籠を目にすると「お盆だなぁ」と感じます。
しかし最近では、盆灯籠にかわり以下の様な木札を立ててあるお墓も増えてきました。

この木札は、塔婆(とば、または とうば)という名前で販売されているもの。1メートルを超える大きな盆灯籠に対し、塔婆はハンディサイズ。
価格面では、盆灯籠は1本あたり1000円弱が相場なのに対して、塔婆は1枚200円弱と手頃で場所も取らない事などから、ニーズが少しずつ高まってきているようです。
ただし、塔婆に「南無阿弥陀仏」が書かれてある場合、それを嫌がるお寺もあるため注意が必要です。
お盆のお墓に置かれる塔婆の「南無阿弥陀仏」が、嫌われる理由
広島のお盆のお墓にも増えてきた「塔婆」ですが、スーパーなどで売られているものも多くが「南無阿弥陀仏」と書かれています。
しかし、一部のお寺などでは南無阿弥陀仏と書かれた塔婆を置くことを嫌がります。その理由は、南無阿弥陀仏という言葉の意味にありました。
南無とは「礼拝またはお辞儀」、阿弥陀とは「仏様の名前」(参照)。お盆が終わって盆灯籠などと一緒に処分する際に、仏様の名前が書かれた札をゴミとしては捨てられない…というのが、嫌がられてしまう理由。

こういった場合には、倶会一処(くえいっしょ)と書かれた塔婆もあるため、こちらを利用すると良さそうです。
倶会一処とは
浄土教の往生の利益の一つで、極楽往生したら先に極楽へ往っているご先祖や親しい人たちに会えるという意味。 via.浄土宗
大きくて場所もとってしまう広島の盆灯籠ですが、昔は盆灯籠の中にロウソクで灯りをともしていた時代もあったのだそう。カラフルな和紙が灯りに照らされて綺麗だったのでしょうね。
火事や小火の問題から、近年は火を灯すことは無くなってしまった広島の盆灯籠ですが、広島らしい風景の1つとして残って欲しい気もします。
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- キャンプでお好み焼!スノーピーク×オタフクコラボで キット飯からガチ勢向けギアも
- 閉城カウントダウン!広島城メモリアルデー 入館無料・御城印作りも
- 5月7日はコナモンの日!たまらん、広島のコナモンたち
- ビッグカツに「みそカツ」「ハムカツ」味があることを知っていたか
- 広島と近郊の「鯉のぼりスポット」まとめ、この時期だけの大空泳ぐ優雅な姿
- あーコレ好きなやつ。ある日、恋した「あんバターもみじ」お土産や差し入れに