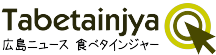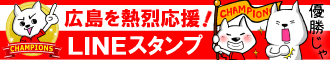公開:2013/10/24 伊藤 みさ │更新:2021/01/07
おせちを食べるマナー、一つひとつに意味がある和食の世界
- タイトルとURLをコピー
- 一般ニュース


お正月に家族や親戚と共に頂く祝い膳、「おせち」。おせちの意味や おせちを食べるマナーをご紹介します。
お正月に家族や親戚と共に頂く祝い膳、「おせち」。1年のはじまりを祝い、神様にお供えしたものを分かち合う事で結びつきを深め、その恩恵を預かるという意味があります。和食には 箸の取り方から作法・マナーがいろいろとあるものですが
おせちを食べるマナー もたくさんありそう。和食がユネスコの無形文化遺産に登録されるという事で、日本人として改めて知っておきたいですよね。お呼ばれする事も多いお正月、人前で食べる時に押さえておきたいマナー・作法をまとめました。

おせちを食べるマナー の前に、まずは「おせち」とは?から。
保存のきく料理が多いのは お迎えした年神様が静養できるよう 台所で騒がしくしないため/神聖な火を使うのを慎むため/多忙な女性が少しでも休めるように などと言われています。
おせちはお重に詰められており、通常は3段から5段ほどあり「福を重ねる」という意味もあるそうです。
目上の人から箸をつける!押さえておきたい、おせちを食べるマナー
お重につめられたおせちは食卓の真ん中に置かれるため、「どれからとっていけばいいのか…」と頭を悩ませる人も多いのでは。
基本的には一の重、ニの重…と一番上の段から取る とされていますが、どの段にどんなものが詰められているかは基本的にしきたりがあるそうなので これを把握しておくとよさそう。
ニの重には「焼物」:ブリ・鯛・エビなど縁起の良い海の幸
三の重には「煮物」:れんこん・里芋・くわい など山の幸
与の重には「酢の物・和え物」:紅白なます・菊花かぶなど日持ちのする生野菜
五の重は「控えの重」:年神様から授かった福を詰める場所として空けておく
※時代や地域などによって異なる場合もあります
また、おせちを食べる時は慶事用の「祝い箸」で頂きます。
祝い箸は両端が細くなっているのは 片方は人が食べる方 もう一方は神様が食べる方 と決まっていて、「神様と共にに食べる」という意味がある。このため「反対側を取り箸として使う」というのはタブー。
この他、食卓を囲んだ際の 目上の人・長老から箸をつける/お重の端側からとっていく というのもあるようです。マナーももちろん大切ですが、せっかく共にしたお祝いの膳なのでその場を楽しむのも大切ですね。
Via. 特集 おせち/All About
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- 週刊・マツダ RX-7創刊、8分の1スケールのハイクオリティモデルはエンジンも緻密に再現
- 小学生の乗船無料!2025「こどもの日」全国の船・フェリーがキャンペーン実施
- 日本版 大学ランキング2025、東北大強し!4分野から測定・トップ50発表
- 2025年のご来光!元旦【初日の出】時刻、都道府県別一覧
- 厄年・八方塞がり、2025年に気を付けたい年齢と生まれ年一覧
- 発表!Yahoo検索大賞2024、都道府県別ではローカルワードがズラリでおもしろい